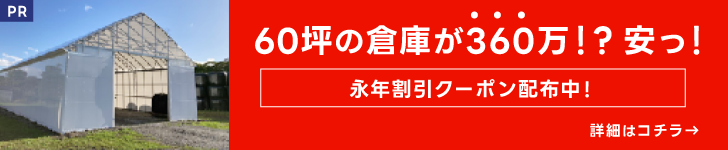施工ナビコラム
施工ナビコラム
北海道でビニールハウスを活用した陸上養殖の事例

北海道におけるビニールハウス陸上養殖の展望と事例紹介
北海道は水産資源の宝庫であると同時に、寒冷地特有の厳しい自然条件も抱えています。そんな北海道で近年注目されているのが、「ビニールハウスを活用した陸上養殖」です。本記事では、ビニールハウス型陸上養殖の基本から、そのメリット・デメリット、北海道内の事例を紹介します。
北海道における陸上養殖の概要
陸上養殖とは、海や川を使わず、陸地に設置した水槽や設備の中で魚介類を育てる方法です。北海道はその気候条件から、外海の養殖が冬季に難しくなるため、屋内施設での養殖に適しています。地下水が豊富で水質も良いため、閉鎖循環型の陸上養殖との相性が良いとされており、持続可能な水産業として道内外から注目されています。
ビニールハウス型陸上養殖のメリットとデメリット
メリット
-
初期費用の低さ
鉄骨やRC造の建物よりも安価に設置でき、導入障壁が低い。 -
太陽光を活かした水温管理
晴天時の自然な加温が可能で、光合成が必要な藻類養殖にも向いている。
※熱を遮断する場合、熱を遮断するフィルムや遮光ネットなど内部に取付など可能。 -
レイアウト自由度が高い
養殖池の数や配管レイアウトの変更が容易で、規模拡張にも柔軟に対応。 -
耕作放棄地の活用が可能
農地転用や遊休施設の再利用にも適しており、地方創生と親和性が高い。
デメリット
-
雪害対策が必要
北海道では積雪による倒壊リスクがあり、屋根勾配や除雪体制が重要。 -
断熱・加温コストがかかる
特に冬期は凍結対策や水温維持に灯油や電気代が発生。 -
結露による腐食リスク
湿気や温度差によってビニールの内側や構造部材が劣化しやすい。
北海道内におけるビニールハウス陸上養殖の主な事例(20件以上)
-
エア・ウォーター株式会社(東神楽町)
トラウトサーモンを養殖する「杜のサーモンプラント」。地下水利用で水温が安定。 -
美唄市・ホワイトデータセンター構想(美唄市)
サーバー熱と雪冷房を活かし、アワビの陸上養殖に挑戦。 -
白老町のホッケ養殖実証(白老町)
タラコ加工場内でホッケ親魚を放流し、2027年の出荷を目指す。 -
美深町営チョウザメ施設(美深町)
1992年からチョウザメを養殖。観光施設も併設。 -
北海道大学水産学部(函館市)
ウニの餌となるマコンブをビニールハウスで養殖。ウニ・アワビ・サーモンも対象。 -
北海道立総合研究機構(留萌市)
ウニの飼育技術をビニールハウス内で研究開発。 -
ニセコ町温泉熱活用プロジェクト(ニセコ町)
バナメイエビの陸上養殖に温泉熱を活用。 -
鷹栖町地域協働型ギンザケ養殖(鷹栖町)
地元企業と共同で冬季も育成可能なハウス施設を導入。 -
森町6次産業推進プロジェクト(森町)
ビニールハウスを利用してブリ・マスを試験的に飼育。 -
利尻町稚魚センター(利尻町)
ナマコの稚魚育成を目的にハウス施設を使用。 -
釧路市ベンチャー企業(釧路市)
日本初のシロサケ陸上養殖実証を開始。 -
余市町ハウス型サクラマス試験養殖(余市町)
果樹栽培用ハウスを転用し、冬季でもサクラマスを育成。 -
北見市農業法人(北見市)
農業ハウスを転用し、淡水魚の試験養殖を実施。 -
登別市ウニ養殖実験(登別市)
地熱を活かし、ビニールハウス内で高密度飼育に挑戦。 -
紋別市冷凍水産企業(紋別市)
副産物を活用しながら、ヒラメをビニールハウス内で養殖。 -
稚内市産学官連携事業(稚内市)
コンブとアワビを組み合わせた「複合養殖」の実証研究。 -
浜中町バナメイエビ試験(浜中町)
保温ハウス内で温水を活用した実験を開始。 -
上川町民間主導プロジェクト(上川町)
森林資源由来のバイオマス熱を利用して魚類を育成。 -
網走市内事業者(網走市)
道産ホタテ稚貝をビニールハウス内で中間育成。 -
札幌市近郊・大学連携プロジェクト
工学系学部と連携してウナギ養殖の実証事業を展開中。 -
小清水町・有機肥料活用型養殖
農業と連携したクロスオーバー型のウニ・昆布養殖に挑戦。
まとめ
北海道におけるビニールハウス型陸上養殖は、コストパフォーマンスの良さや設備導入の柔軟性に優れた持続可能な手法として注目されています。特に地下水や温泉熱、雪冷房など、北海道特有の自然資源との親和性が高く、今後の拡大が期待される分野です。
事例からもわかるように、行政や大学、民間企業の連携によって多彩な取り組みが進行しています。新たに養殖事業を検討している方は、ぜひこうした地域性や既存事例を参考に、ビニールハウス型陸上養殖の可能性を探ってみてください。