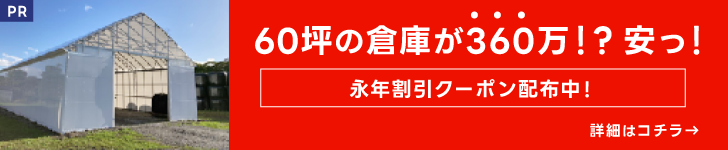施工ナビコラム
施工ナビコラム
陸上養殖フグ・トラフグとビニールハウスの活用事例

陸上養殖フグ・トラフグとビニールハウスの活用事例
近年、持続可能な水産業の一環として注目を集めているのが「陸上養殖」です。中でも高級魚であるフグ・トラフグの養殖は、安定供給と品質管理の面から多くの事業者が導入を進めています。本記事では、ビニールハウスを活用したトラフグ陸上養殖に焦点を当て、基本知識から導入事例、施工業者の選定ポイントまでをわかりやすく解説します。
ビニールハウスを活用した陸上養殖の基本知識
陸上養殖とは?
陸上養殖とは、海や河川を使わず、陸地上の水槽や施設で魚介類を育てる手法です。以下のような特徴があります:
-
病気のリスクが低い(外部の病原体の侵入を防げる)
-
水質管理がしやすい(ろ過装置・センサーなど活用)
-
土地活用の自由度が高い(内陸部でも可能)
-
近郊流通ができる(消費地近くで育てて即出荷)
ビニールハウスが活用される理由
陸上養殖における施設として、ビニールハウス型構造が選ばれる理由は以下の通りです:
| 項目 | メリット |
|---|---|
| コスト | 鉄骨・コンクリート構造に比べて建設費が安い |
| 断熱 | ダブル被膜等の仕様で温度管理がしやすい |
| 柔軟性 | カスタマイズが容易(換気窓、設備導入) |
| メンテナンス |
経年劣化にも対応しやすく、更新も低コスト |
トラフグの陸上養殖の基本知識
トラフグとは?
**トラフグ(学名:Takifugu rubripes)**は、日本国内では高級魚として扱われるフグ類の一種で、特に冬の鍋料理などに人気があります。毒を持つことで知られていますが、陸上養殖では毒の管理・無毒化処理も可能です。
トラフグ陸上養殖の主な特徴
-
水温:20〜25度に保つ必要あり
-
餌管理が難しく、餌の質が味に影響
-
成長速度は約1年で1kg前後
-
サイズ・味の均一化が可能
-
収穫期が計画できる(周年出荷)
陸上養殖フグの生産方式
| 方式 | 内容 |
|---|---|
| 循環式養殖システム(RAS) | 水を再利用し、ろ過・殺菌を繰り返す |
| オープン式水槽 | 井戸水や地下水を使用、排水を流す |
RAS(Recirculating Aquaculture System)は初期コストがかかりますが、ビニールハウスと組み合わせることでトータルコストを抑える事が可能です。
トラフグ陸上養殖市場の現状と今後の動向
国内市場動向
-
国内では天然漁獲量の減少により養殖フグの需要が拡大
-
山口県、熊本県、愛媛県などがフグ養殖の主要地域
-
飲食業・観光業の需要回復に伴い出荷単価が回復傾向
陸上養殖に参入する理由
-
海域使用の制限回避(漁業権の問題)
-
環境変化(赤潮・台風)からのリスク回避
-
都市近郊への立地で物流・販売が有利
ビニールハウスを活用したトラフグ養殖の事例
事例①:熊本県天草市・民間養殖業者(2023年〜)
-
施設概要:鉄骨ビニールハウス内にFRP水槽を設置(10トン級水槽×4基)
-
水温管理:ヒートポンプ+断熱カーテン+ダブル被膜
-
成果:出荷サイズまでの育成期間が海面養殖より短縮(約10ヶ月)
-
導入効果:
-
冬季も安定出荷可能(飲食店・旅館への直販)
-
天候リスクゼロ(赤潮・台風影響なし)
-
事例②:兵庫県淡路島・農業法人による複合経営(2022年〜)
-
ビニールハウス:農業ハウス(元花き用)を再利用
-
養殖内容:野菜ハウスの隣でトラフグ水槽を併設
-
狙い:
-
余剰エネルギーの活用(暖房・ヒートポンプ)
-
地産地消のモデル化(農業×養殖の複合経営)
-
ビニールハウス・養殖設備の施工業者選びのポイント
ビニールハウス施工業者の選び方
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 経験 | 陸上養殖案件の施工実績があるか |
| 断熱・換気技術 | ダブル被膜、カーテン、強制換気対応が可能か |
| 構造設計 | 水槽や機械設置に合わせたカスタム設計ができるか |
| アフター対応 | 修理・点検・増設への柔軟性があるか |
代表的な業者例(北海道・本州共通):
-
丸二物産(北海道)※農業用倉庫にも対応
-
東都興業(全国対応)
-
渡辺パイプ(施設園芸+水関連部材も取扱)
養殖設備業者の選び方
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| RAS技術の有無 | ろ過・UV殺菌・水質センサーなどの導入経験 |
| 実績 | トラフグや海水魚の取り扱い実績があるか |
| サポート体制 | 水質分析、稚魚導入、餌管理の支援があるか |
有名な設備業者例:
-
フルタ電機(ポンプ・制御系)
-
リバネスアクア(バイオ系スタートアップ)
-
有明水産機器(トラフグ向けの実績あり)
まとめ:トラフグ陸上養殖×ビニールハウスは有望な新規事業モデル
フグ・トラフグの陸上養殖は、高収益性・ブランド化の可能性があり、ビニールハウスの活用により初期投資を抑えつつ、環境制御がしやすくなるという大きなメリットがあります。農業法人や地方自治体との連携、補助金活用などを通じて、持続可能で高付加価値なビジネス展開が期待されます。
補助金・助成金の活用も検討を!
国や自治体のスマート水産業支援事業や、**農業水産複合化支援(6次産業化補助金)**などを活用することで、導入コストを大幅に抑えることが可能です。
事例を4つ+α:陸上養殖フグ・トラフグ × ビニールハウス(または類似施設)の具体例
以下に、「ビニールハウス活用」または「施設を屋根・ハウス構造で囲む」などの類似要素がある、トラフグ・温泉トラフグの陸上養殖事例を4件+追加3件紹介します。
主な4つの事例
| 事例名 | 所在地 | 施設構造・特徴 | 養殖規模/成長管理・特徴 | 成果・課題など |
|---|---|---|---|---|
| 事例①:栃木県那珂川町・株式会社夢創造「温泉トラフグ」第2プラント | 栃木県那珂川町 | 廃校となった小学校に隣接するビニールハウスを使った第2プラント。水槽は12t ×4基で、42t規模。 元祖温泉トラフグ | 温泉水を利用。冬季でも温度を保てるため、成長遅延が少なく、目標サイズ(800〜1,000g)までの育成を1年以内で可能にすることを目指している。 元祖温泉トラフグ | 成長速度の改善、周年出荷の可能性あり。ただし初期投資・運用コストがかかる。水質管理等の技術力が必要。 |
| 事例②:茨城県北茨城市 あんこうの宿 まるみつ旅館 | 茨城県北茨城市 | ビニールハウス内に円柱形水槽6基(直径約4m)を設置。温泉水を混ぜた人工海水を使用。ハウスの寸法は長さ約35m、幅約7m。 きたかんナビ | 約500尾の試験的飼育から開始。将来的には2,000匹規模までを想定。温泉の割合・塩分調整・温度管理を段階的に改善。 きたかんナビ | 宿泊客等への提供を狙う地域型のモデル。魚の健康・水質制御・コスト回収が課題。魚の寄生虫アニサキス等のリスク管理も重視している。 |
| 事例③:奈良県天川村・下西勇輝さんのトラフグ養殖 | 奈良県天川村 | 廃校になった旧小学校(校舎)を利用。教室などを水槽設置場所に転用。ハウス構造かビニールハウスそのものという記述は限定的だが、屋内施設の活用が特徴。 PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) | 初出荷:約124匹、体重約1kgサイズ。山深い地域で陸上養殖を実現。地元流通・飲食店との協力など地域ブランド化を目指す。 PRESIDENT Online(プレジデントオンライン) | インフラの整備コスト、人手・ノウハウの確保が大きなハードル。気温変化などの管理も重要。 |
| 事例④:株式会社アクアステージ 滋賀県大津市東部 | 滋賀県大津市 | 完全閉鎖環境(閉鎖循環式陸上養殖システム)で内陸にてトラフグ試験養殖。建物等を利用、ビニールハウスの記載が明確にビニールハウス型かどうかは限定的だが、施設での囲われた屋根等管理施設として類似の条件がある。 株式会社アクアステージ | 約2,000匹規模での試験。IoT 管理などを取り入れ、水替えを抑える水質浄化技術を利用。地域特産化を目指してブランド認証の準備も。 株式会社アクアステージ | 完全閉鎖式での運用はコストがかかるが、水質安定性や魚の健康維持には有利。出荷のタイミング・販路確保が課題。 |
その他の追加事例・類似取り組み
以下の3件は「温泉水養殖」または「施設(廃校・ハウス等を流用)」型で、ビニールハウス活用または類似施設のヒントが得られるものです。
-
事例⑤:愛知県美浜町「ちた福」プロジェクト
愛知県知多郡美浜町で、観光協会と共同して「ちた福(ふぐ)」の陸上養殖に挑戦中。旅館等と連携し、夏ふぐ料理を提供。施設構造の詳細については「ビニールハウス」が明記されていないが、陸上養殖+地域店舗連携のモデルとして参考。 プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES -
事例⑥:奥村組「太平のとらふぐ」試験販売・実証実験棟(茨城県つくば市)
2021年11月に実験棟を建設し、閉鎖循環式陸上養殖を行い、「太平のとらふぐ」として加工商品を試験販売。施設における屋根・管理設備等が整備されており、ハウス型管理の要素あり。 奥村組 -
事例⑦:「温泉トラフグと天然トラフグ」施設(栃木県那珂川町内)
株式会社夢創造の取組で、第2プラントがビニールハウスを活用して設置されている。これが上述の事例①と重なるが、複数のプラントがあり、「ビニールハウスを施設の一部として使う」実際の構造が確認できる。 元祖温泉トラフグ+1
写真付き・構造データありの事例
事例A:山口県・長門市「長州ながと水産(安藤建設)」陸上養殖施設
-
規模・収容量:水槽80基にて、稚魚40,000尾・成魚30,000尾以上、合計70,000尾以上を養殖。 note(ノート)
-
構造・建屋:完全なビニールハウス構造とは明言されていませんが、屋根付き・屋内管理されており、外光や建屋内への敷設がなされている大規模施設。撮影写真が複数あり、屋根・建屋内の水槽が見える。 note(ノート)
-
被覆・温度管理:具体的な被覆材(ビニール被膜・断熱材)の仕様は公開されていませんが、「陸上養殖施設」という性質から、冬季含む温度・水質管理設備ありとされており、外気温に左右されにくい設計が見られる。 note(ノート)
-
コスト・運用:細かい建設コストの数字は公表されていませんが、建設業を主体とする会社が養殖事業を立ち上げており、設備・運用コストを見込んで事業計画を作っているとの記載。利益確保の見込みの上で、事業拡大を目指している。 note(ノート)
事例B:兵庫県朝来市・旧幼稚園舎を活用した陸上養殖(中村さんの取組)
-
施設の転用:旧竹内幼稚園等の旧園舎を借用。園舎の建物を飼育施設として再利用。屋根・壁がある建築物の中で養殖する形。 神戸新聞
-
養殖規模・稚魚数:稚魚を約6,000尾放す予定。出荷サイズ約1kgを目指す。神戸新聞
-
期間:天然物で2年かかるところを、陸上養殖では約1年を目標。理由は温度管理がしやすいため。神戸新聞
-
写真:旧幼稚園舎の外観、施設の様子の写真あり。建物を流用した構造のため、ビニールハウスではないが、屋根付き管理施設として類似の点が多い。 神戸新聞
事例C:「温泉トラフグ」(栃木県那珂川町)
-
-
施設構造:廃校となった旧武茂小学校の教室を使い、水槽(1教室に12トン水槽を1基ずつ、5教室)を設置。屋根・壁が小学校建築。ハウス型被膜とは異なるが、屋内施設で温泉水利用、管理された環境。 ウィキペディア
-
被覆/温度管理:温泉水を使うことで、水温維持コストを抑える試み。教室等を施設として再利用することで、建築コスト・被覆材コストの代替とする設計。 ウィキペディア
-
写真:Wikipedia記事に養殖の様子を撮った写真が複数。外観・水槽の様子あり。 ウィキペディア
-
コスト情報:建物は町から教室の無償提供。設備費として町が拠出した金額30万円(設備費として)という記録あり。水槽容量や教室数との比較から、初期設備費はそれ以外にも大きくかかっているが、施設コストをかなり抑える設計になっていた。
-
比較・考察:ビニールハウスを使った事例の特徴
これらの事例を比較すると、以下のようなパターンと特徴が見えてきます:
-
温泉水の利用 が多く、ビニールハウス等を屋根や囲いとして使い、温度維持・保温対策を強化している例がある。
-
施設の転用(廃校舎、小学校、プール・施設跡)を使うことでコストを抑え、屋根・建物を活かして養殖施設とする例が多い。
-
ビニールハウス内水槽という明確な構造が確認できるのは「茨城県あんこう宿」「栃木県那珂川町の第2プラント」など。これらは被覆材を用いたハウス構造で水槽を包む形。
-
養殖の 規模 は試験段階〜小規模〜中規模、多くは試験養殖や事業化準備中であり、まだ大規模商業化しているケースは少ない。
-
成長期間・温度管理・水質管理技術が成功の鍵。特に冬季の保温/水温変動対策が重要。